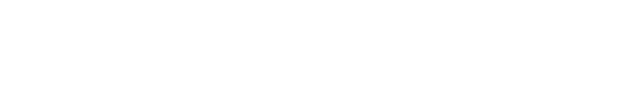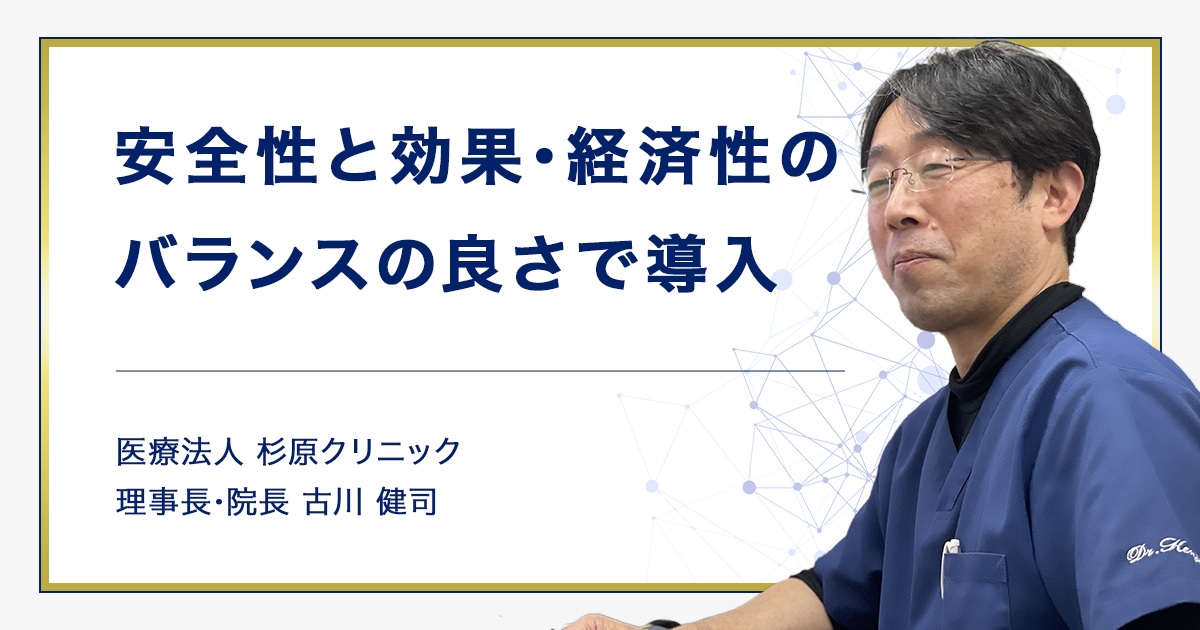発熱・せき外来(予約不要)
診療の内容:インフルエンザ、新型コロナの抗原検査を実施中!
当院の特徴:
当院では、かかりつけ患者さん以外にも、発熱の患者さんの診察行っています。しかし、発熱者が待機できる専用スペースが3組しかないため、37.5℃以上の発熱のある患者さんは、可能であれば、クリニックの前に駐車場がありますので、自動車での来院をお願いしています。
#65歳以上の方、持病のある方には検査陽性確定後、ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバを処方することが可能です。
■長引く咳、ひどい咳
百日咳やマイコプラズマ肺炎の疑いのある方の、受診をお待ちしています。
1.百日咳とは
百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作(痙咳発作 )を特徴とする急性の気道感染症です。
百日咳は世界的に見られる疾患で、いずれの年齢でもかかりますが、小児が中心となっています。母親からの免疫が十分でなく、乳児期早期から罹患する可能性があり、乳児(特に新生児や乳児期早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに死に至ることもあります。
主な症状
経過は3期に分けられ、全経過で約2~3カ月で回復するとされています。
1. カタル期(約2週間持続) :かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。
2. 痙咳期 (カタル期の後に約2~3週間持続):次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)となります。夜間の発作が多いですが、年齢が小さいほど症状は多様で、乳児期早期では特徴的な咳がなく、単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ(顔色や唇の色や爪の色が紫色に見えること)、けいれん、呼吸停止と進展することがあります。合併症としては肺炎や脳症などもあり特に乳児では注意が必要です。
3. 回復期:激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなります。成人の百日咳では咳が長期にわたって持続しますが、典型的な発作性の咳を示すことはなく、やがて回復に向かいます。全経過で約2~3カ月で回復します。
検査方法:当院では、百日咳菌に対する抗体(IgM/IgA)を測定を検討しています。
治療方法
生後6カ月以上は、抗菌薬による治療を行っています。また、咳が激しい場合には咳止め等の対症療法を行います。
マクロライド系抗菌薬(アジスロマイシン、エリスロマイシンなど)が主に使用されます。(厚労省HPより)
予防
乳児のいる家族やこれから出産を希望している家族(両親、兄弟、同居の祖父母なども)はとくに、自身が感染しないよう、また乳児に感染させないよう、予防接種を含めた感染予防対策が大切です。
日本では乳幼児期にDPTまたはDPT-IPVワクチンを接種しますが、4-12年で免疫力は低下するため3)、小・中学生を含めた学童や成人はワクチンによる追加接種で免疫をつけることが望ましいです。
日本でも三種混合ワクチン(トリビック®)が11-12歳及び成人に接種が可能です(任意接種)。今後、学童期に対して百日咳含有ワクチンの定期接種が追加されることも検討されています。
公園の街クリニックでは、三種混合ワクチン(トリビック®)の接種予約を受け付けています。(現在、出荷調整中)
2.マイコプラズマ肺炎とは
頑固なせきをともなう呼吸器感染症。小児や若い人に比較的多い。
マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ( Mycoplasma pneumoniae )」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。小児や若い人の肺炎の原因として、比較的多いものの一つです。例年、患者として報告されるもののうち約80%は14歳以下ですが、成人の報告もみられます。マイコプラズマ肺炎は1年を通じてみられ、秋冬に増加する傾向があります。
主な症状
発熱や全身の倦怠感(だるさ)、頭痛、せきなどの症状がみられます(せきは少し遅れて始まることもあります)。せきは熱が下がった後も長期にわたって(3~4週間)続くのが特徴です。肺炎マイコプラズマに感染した人の多くは気管支炎で済み、軽い症状が続きます(一般に、小児の方が軽症で済むと言われています)が、一部の人は肺炎となったり、重症化したりすることもあります。また、5~10%未満の方で、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されています。
検査方法:胸部聴診、血液検査、レントゲンを総合して判断します。
治療方法
マイコプラズマ感染症は、マクロライド系などの抗菌薬で治療されます(※)。軽症で済む人が多いですが、重症化した場合には、入院して治療が行われます。せきが長引くなどの症状がある時は、医療機関で診察を受けるようにしましょう。また、マクロライド系抗菌薬が効かない「耐性菌」に感染した場合は他の抗菌薬で治療します。(厚労省HPより)